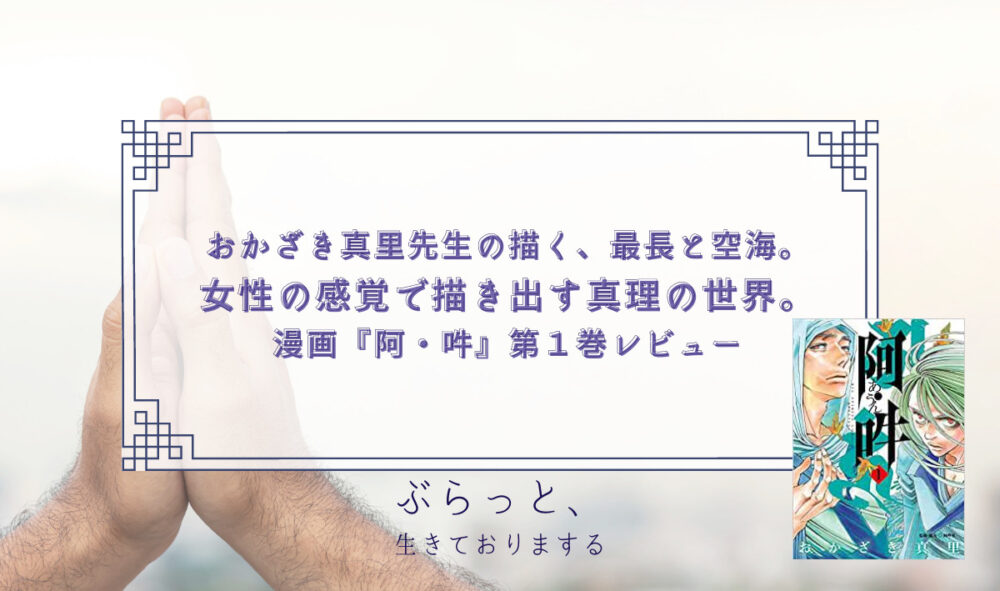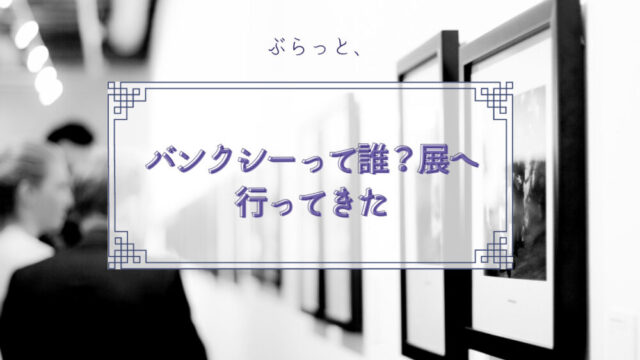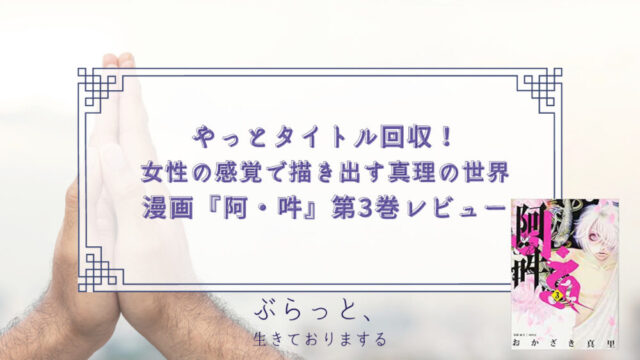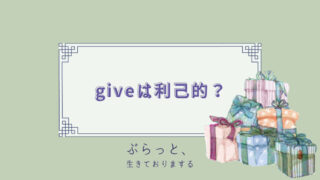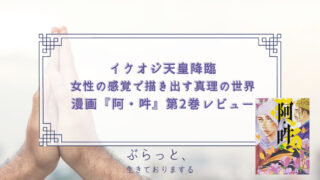こんにちは、いぇんです。
本棚に入ってるものを紹介していく「ぶらっと、本棚」シリーズ第三弾です。
今回は最澄と空海の漫画です。描くのはおかざき真里さん。
これまで女性向けのストーリーと絵で女性ファンの心を鷲掴みしています。
主なテーマは恋愛、働き方、生き方など。
おかざき真里さんは多摩美術大学卒で、
時にグロテスクさを感じられるほどの細やかで猛烈な描き込み特徴です。
画面の美しさと儚さ、そして独特の間の取り方が魅力的な作品が多いですが、
ここにきて突然の宗教漫画!?
どうした!?いや、どうなる!?とわくわくで一杯の漫画のご紹介。
第一話 最澄と空海
これ空海(少年)ですよカッコ良くないですか?笑
最澄と空海のそれぞれの生い立ち、仏門に入るまでの幼少期のお話です。
ほとんど同年代の二人ですが、まだ顔を合わせるのは先の話です。
二人とも幼少から天才と称され学ぶ機会を与えられる様子がわかります。
挿絵は、大学で与えられたカリキュラムで学ぶことに飽きた真魚(のちの空海)が、
近くのお坊さんに殴り込んでくる様子です。知識への渇望で溢れています。
一方の広野(のちの最澄)は山の端から溢れる光に涙してしまうような感受性の強い子。
周囲の期待に応えるように学びながら、若年で当時でいう国家公務員である僧籍に入ります。
しかしそこは権力と結びついていて仏の教えとはかけ離れた世界。
最澄は傷心し寺には入らず俗世から離れ山に籠ることを決めます。
第二話 阿刀大足(あとのおおたり)
第二話は15歳となった真魚(のちの空海)が平城京を訪れ叔父の元で大学に入る場面。
幼い頃から聡明で、知識欲の塊。
レベルの違う知識を学べると期待した大学で出会った経典にも、一瞥してガッカリしてしまいます。
挿絵は夜長に山中に出て自ら崖から身を投げる荒業を行う真魚と出会う勤操和尚。
真魚は政の中ではなく、生命の渦中にこそ真理を見出せると信じています。
第三話 勤操(ごんぞう)
真魚は第二話で出会った勤操和尚(ごんぞうかしょう)の元に顔を出すようになり、
そこで仏教の言葉を、人の声を通して少しずつ学びます。
返礼として山で掘り出した辰砂(個体の水銀)を渡す場面もあります。
余談ですが辰砂(しんしゃ)は宝石の国にもメインで登場する鉱石の一つです。
水銀というと毒のイメージが強いですが、中国では顔料、漢方薬として用いられ、
非常に高価なものでありました。

真魚(のちの空海)は15歳でエリート出世コースである大学を辞めてしまいます。
勤操和尚は真魚が感じている欠乏感に対して、仏教の経典を学ぶ道を示唆します。
それは抜けられない沼に落ちる覚悟を求めるものですが、
真魚はそれをあっさり受け入れます。
「犀の角の如くただひとりゆけ」という言葉を添えて。
晶文社という出版社のロゴマークは犀(さい)のマークです。
この出版社さんの本は面白いものが多い印象です。
下記の創業時の挨拶文より、尖った本を出すという心意気が感じられます。
何者にも媚び諂ったりせず、自身の目先鼻先に確固たる指針を携えて、
犀の角のように一人でも孤高に歩き、進む。
そういう姿が、今後の最澄と空海を通して描かれます。
私どもは、このたび晶文社という名のささやかな書肆を開きました。俗にいう山椒は小粒でもピリリと辛いの意気です。もっとも尖端的で、同時にもっとも伝統的なもの、要するに語の根源的な意味でのラジカルな出版物を出したいというのが私どもの願いです。
(昭和36年4月、当時の代表取締役 中村勝哉による創業の御挨拶より抜粋)
公式ホームページ
第四話 泰範(たいはん)
第四話では最澄の一番弟子となる泰範(たいはん)が登場します。
愛嬌よく振る舞い、他人が望む言葉や態度を与えることで、
クソみたいと評する社会を生きのびて、寺にやってきました。
とても俗人的で私たち現代人の感覚にとても近い振る舞いをします。
他人の弱っている心を見抜き、傷口に欲しがっている言葉を与え、
自分を必要不可欠な存在であると思わせることが彼の処世術です。
第五話 山の中
勤操和尚を通じて、最澄と空海が近づいていきます。
挿絵の場面は水行をしている最澄を真魚が一方的に見つけたという場面です。
真魚はその光景を「美しい!」と褒めると同時に、
仏教を学ぶほどにあの曇りなき清らかさを知ることができるのでは、と
仏教の道に希望を感じ取る、そういう出会いの場面となっています。
女性の描く、宗教
以上、第一巻の感想でした。
これは女性作家の描く最澄と空海の漫画です。
教義や歴史的経緯の説明もちろん大事ですが、
目に見えないものを読み取ろう、そしてそれを文字や漫画で描こうという行いがそもそも修行であるようにも思えます。
おかざき真里先生は女性視点の漫画をたくさん描いていて、
「もう、そう!そうなんだよ!!」
「その違和感!!よく描いてくれました!!!」と思ったことは数知れず。
やるせなさ、自分の弱さ、自分の殺し方、社会の生き方。
そんな共感というか救いを何度もらったかわかりません。
とても繊細な視点を持っているんです。
女性の言葉は感覚的だとかで理解されないことが多いです。
論理的に説明できないと劣っているかのような判断をされることもあります。
一方で最近は女性の言葉、女性の感性を経由して流れる言葉そのものをもっと感じ取るべきでは?という主張もされます。
おかざき真里先生の、繊細な視点と線とで描かれる宗教の世界観。
ゾッとするほど美しい場面がこれからも続きます。
同時に、この阿吽という作品は、すごく荒々しいタッチで描かれることが多いです。
おかざき先生の新境地では?と勝手に思っています。
真理を前に圧倒されるという迫力を図太く荒々しい線で表していて、
おかざき先生も挑んでいらっしゃる…!なんて応援したくなる気持ちです。